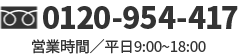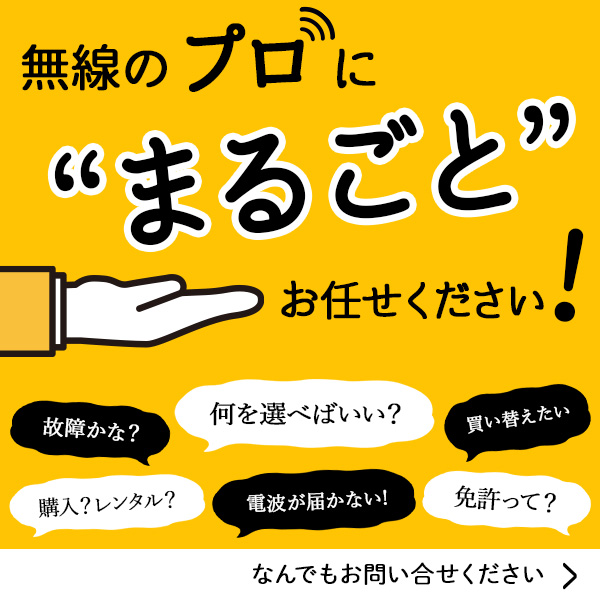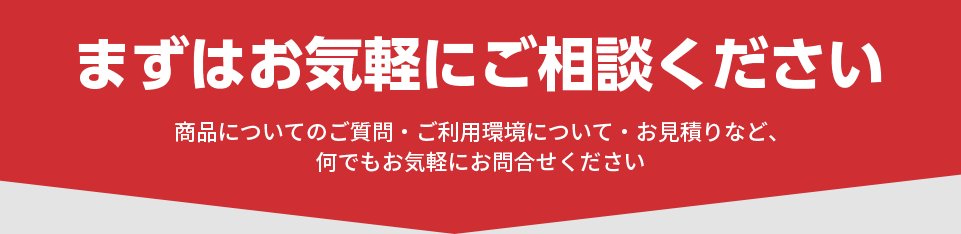店舗運営を改善する方法とは?改善する際のポイントや「ECRSの原則」について解説

接客業務や販促、売上管理など、店舗運営に関わる業務は様々なものがあります。どれも重要な業務ですが、開店中は顧客満足度や再来店を決定づける接客業務が大きなウェイトを占めている状態です。
人手不足が深刻化している中で接客業務に注力しながら、必要な事務作業を捌いていくためには、店舗運営の改善が欠かせません。
今回は店舗運営の業務や店舗運営の主な課題、改善する方法やポイントについて解説します。
店舗運営の業務
店舗運営の業務は次の7つです。
- 接客業務
- 販促
- 売上管理
- 開店・閉店業務
- 人材管理・教育
- 仕入れ・在庫管理
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.接客業務
接客業務は、レジ打ちや商品・サービスの提供など、営業中に生じる顧客とのやりとりすべてが該当します。顧客満足度や再来店を決定づける要因となることから、店舗運営の中でも特に重要な業務の1つです。
そのため、接客業務は丁寧な言動を意識する必要がある他、高いコミュニケーション能力や商品の専門知識などが求められます。
2.販促
販促は、商品・サービスの販売促進を行う業務のことです。SNSや広告配信、販促イベント、割引などが該当し、顧客に商品・サービスを知ってもらい、来店してもらったり、購買意欲を高めたりします。
販促業務は顧客ニーズや好みに合わせて行う必要があるため、顧客管理やマーケティング調査などが欠かせません。近年はツールを活用した自動化も進んでおり、年齢や性別、購買履歴などのデータを分析したうえで、スマホアプリのプッシュ通知で情報を訴求する店舗も増えてきています。
3.売上管理
売上管理は、店舗の売上高や利益、在庫状況などを管理し、店舗の経営状態について分析する業務のことです。日・週・月・年単位で売上目標を設定し、目標達成に向けて販売計画を立案・実行し、結果を分析しながら、なぜそういう結果になったのか要因を探り、次に活かしていきます。
また、売上管理は売上を把握するだけでなく、在庫管理や客数、客単価など、様々な角度から売上分析を行い、販売計画を立案していかなければなりません。
4.開店・閉店業務
開店・閉店業務は、店舗の開店前もしくは、閉店後に行われる業務のことです。開店前に行われる業務としては主に以下が挙げられます。
- 店舗内外の清掃
- レジの準備
- 商品のチェック・補充・陳列
- 開店スタッフ全員で行う朝礼
閉店後に行われる業務としては主に以下が挙げられます。
- 売上の集計・入金
- セキュリティチェック
- 在庫管理
- 新しいプロモーションの準備
- 店内外の清掃
快適なショッピング環境の提供や、スムーズな店舗運営を実現するためには、開店・閉店業務は非常に重要です。
5.人材管理・教育
人材管理・教育は店舗で働くスタッフに関わる業務のことです。シフト調整や勤怠管理、採用、評価、新人の研修・教育、能力開発研修、キャリアアップ支援などが該当します。
人材管理はスタッフの都合を確認しながら、円滑な営業ができるよう調整する必要があるため、負担が大きい業務です。また、優秀な人材を確保し、店舗の戦力として長く働いてもらうためには、採用や教育、評価の質が左右するといっても過言ではありません。
6.仕入れ・在庫管理
仕入れ・在庫管理は、売上の最大化を図るためには欠かせない業務です。仕入れ管理とは、商品の仕入れ管理に関する業務のことです。
商品を注文してから届くまでの流れをチェックし、正しく仕入れられているかを確認します。
また、仕入れタイミングを考えたり、商品の仕入れコストを低くするための施策を考えたりすることも仕入れ管理の大切な業務です。
在庫管理とは、店舗の在庫状況を管理したり、必要に応じて商品を補填したりする業務のことです。商品が品切れになると売上に悪影響を及ぼす他、あまり販売されない商品の場合は、廃棄リスクが生じます。
在庫の過不足なく最適な状態を維持するためには、的確な仕入れ・在庫管理が欠かせません。
店舗運営の主な課題
店舗運営の主な課題として次の4つが挙げられます。
- 人材不足による業務負荷
- 事務作業が多い
- 本社の指示が店舗で徹底されていない
- スタッフ同士の連携が取れていない
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.人材不足による業務負荷
人材不足による業務負荷は店舗運営の大きな課題です。帝国データバンクが発表した「人手不足に対する企業の動向調査(2023年4月)」によれば、飲食店の人手不足割合は6割を超えています。
また、アルバイトなどの非正社員の人手不足割合は8割を超えています。人材不足の深刻化によって既存の従業員の業務負担が大きくなれば、ストレスの増加やサービス低下など、店舗運営に様々な悪影響を及ぼします。
2.事務作業が多い
売上管理や仕入れ・在庫管理など、店舗運営は意外と事務作業が多いです。しかし、事務作業が多いと、他の業務に割く時間が少なくなってしまうため、接客や人材管理・教育といった業務に集中できなくなってしまいます。
これらの業務が疎かになってしまうと、サービスの低下や売上減少といった問題にも発展しかねません。
3.本社の指示が店舗で徹底されていない
多くのチェーン店を経営している場合、本社からの指示が店舗で適切に実行されていないことも少なくありません。
本社の指示が徹底されていないと、店舗運営の方針や目標がずれてしまい、顧客満足度や業績低下などの問題に発展するリスクがあります。
4.スタッフ同士の連携が取れていない
店舗で働くスタッフ同士の連携が取りづらいのも店舗運営にありがちな課題です。スタッフ同士の連携が取れていないと、無駄な往来が生じるなど、業務の非効率化を招きます。
また、顧客対応が遅れたり、業務のミスや重複などが発生したりするため、サービスの低下や売上の減少にもつながりかねません。
スタッフ同士の連携を強化したいのであれば、無線の導入がおすすめです。無線は1人対1人で音声通信できる携帯電話と違い、複数人に対して音声通信できるツールです。
送信ボタンを押せばすぐに複数人に音声発信できるため、スムーズに情報の伝達・共有が行えます。無線は通信距離別に「特定小電力トランシーバー」「簡易無線」「IP無線」の3タイプがあるため、通信距離や通信環境に合わせた機種の選択が可能です。
また、近年はスタイリッシュで持ち運びしやすい機種や、スマホを無線として使用できる無線アプリなど、無線も多様化してきているため、使用シーンに適した無線も選択できます。
店舗運営を改善する3つの方法
店舗運営を改善する方法として次の3つが挙げられます。
- 業務をなくす
- 業務プロセスの変更
- 業務を削減する
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.業務をなくす
非効率な業務そのものをなくしてしまう方法です。日常的に行っている業務について、店舗運営に必要なのか精査し、不必要であれば業務をなくすことで、業務を効率化できる可能性があります。
例えば、各商品にラベリングしていたものを、陳列棚ごとの価格表示にすることで、ラベリングの時間・手間をなくして販売活動に集中できる環境を整備できます。また、ラベルとシールの消費数も減らせるため、経費削減も可能です。
2.業務プロセスの変更
業務プロセスの変更が業務改善でもっとも知恵が必要となる方法です。業務プロセスの変更はコスト削減を把握しやすく、業務効率アップを実感しやすいといった特徴があります。
一方、変更に伴って、一定のコストが発生する他、場合によっては成功しないリスクがあることも念頭に置いておく必要があります。業務プロセスを変更するパターンは大きく分けて、次の3つです。
- 人:配置・シフトの転換・調整
- ルール・仕組み:システムの導入・変更
- 物:商品自体や商品を製造する設備の変更
人や設備の配置転換も立派な業務プロセスの変更です。したがって、まずはできることから少しずつ改革を進めていくとよいでしょう。
また、コストはかかりますが、店舗をより変革させていくという意味では、注文システムやスマートデバイスなどのICT導入も検討していくことをおすすめします。
3.業務を削減する
業務そのものをなくせない場合、業務回数を削減して、改善していく方法です。例えば、棚卸業務そのものをなくすことはできません。
しかし、各商品の消費期限や販売量によって商品を区分し、週1回・2週間に1回・月1回というように棚卸しを行うスパンを設定することで、棚卸のトータル回数を削減できます。また、配膳ロボットを導入して、配膳・下げ膳の業務を自動化することで、配膳・下げ膳の業務量を削減することも可能です。
株式会社システム情報企画では、配膳ロボットを提供しています。飲食店の業務量を削減したいという場合、配膳・下げ膳の業務自動化によって、業務量を削減できる配膳ロボットの導入を検討してみてください。
店舗運営を改善する際のポイント
店舗運営を改善する際のポイントとしては以下が挙げられます。
- 業務フローの見直し
- マニュアルの策定・共有
- 業務のデータ化
- 店舗運営をサポートするツール・システムの導入
- システムの統合
人手不足が深刻化している中では、ツール・システムの導入および、業務のデータ化による成功事例の蓄積・共有が欠かせません。また、システムを統合することも店舗運営改善には必要不可欠です。
システムがバラバラに機能している場合、各システムにアクセスして必要なデータを抽出し1つのデータにまとめなければならないため、非常に手間がかかります。これでは本当の意味で改善にはつながりません。
システムを統合しておけば、1つのシステムから必要なデータをすべて抽出してまとめられるため、運営改善に寄与しながら効率的にデータを利活用できます。
業務改善に活用できる「ECRSの原則」とは?
「ECRSの原則」とは、業務に潜むムダを削減することで、業務改善を促し、生産性を向上させるフレームワークです。業務改善に活用できる「ECRSの原則」は次の4ステップです。
- 排除(Eliminate)
- 結合(Combine)
- 交換(Rearrange)
- 簡素化(Simplify)
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.排除(Eliminate)
排除しても問題業務を洗い出すステップです。まず、行っている業務の内容や理由、目的を明確化します。
この際、誰も確認していない報告書や必要のない検索項目など、理由および目的が分からない業務の場合、その業務は慣例化しているだけで、意味のないものだと解釈ができます。これらの業務を排除できれば、業務工程を削減して、業務の効率化を図ることが可能です。
2.結合(Combine)
結合は、似ていながら、別々に行っていた業務を一本化するステップです。例えば、様々な測定器を用いていた検査を1台の測定装置で行ったり、複数枚に渡っているチェックシートを1枚にまとめたりすることなどが挙げられます。
業務内容によっては業務を分離した方が効率化できる業務もあるため、このステップでは結合可能か、分離すべきかといった視点で取り組むことが大切です。
3.交換(Rearrange)
交換は設備を再配置したり、業務の順番を入れ替えたりするステップです。例えば、右から左に流れていた業務工程を、人の動きに合わせた左から右に変えることで、流れをスムーズにできます。
また、設備を再配置することで、無駄な往来を減らせるため、改善につなげられます。短縮時間は少ないかもしれませんが、長期的に見れば大幅な業務改善となるでしょう。
4.簡素化(Simplify)
簡素化は業務をパターン化したり、工程の1部を自動化したりして、業務を単純化するステップです。例えば、複数のパラメーターを導入・設定していた装置を、1つのパラメーターを入力すれば自動設定されるようなショートカットを作成すれば、入力を簡素化できます。
また、配膳ロボットを導入して、配膳・下げ膳の業務量を削減し簡素化できれば、別の業務に集中することも可能です。また、業務を簡素化すれば、誰でも同じクオリティで作業できるため、属人化の防止にも寄与できるでしょう。
まとめ
店舗運営は接客業務や販促、売上管理など多くの業務をこなしていく必要があります。どれも店舗運営には欠かせない業務ですが、顧客満足度や再来店を促すためには、開店中は接客業務に注力しなければなりません。
しかし、接客業務ばかりに注力していると、裏方作業が進まず、長時間労働に発展するリスクもあります。人手不足が深刻化しつつある中で、接客業務の質を落とすことなく、必要な作業をこなしていくためには、店舗運営の改善が欠かせません。
そのため、本記事で紹介した店舗運営を改善する方法やポイントを参考にしながら、店舗の運営効率を高めていきましょう。